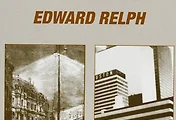建築家・隈研吾が、2020年2月に書き下ろしの新刊『点・線・面』(岩波書店)を上梓した。近年、国立競技場や高輪ゲートウェイ駅駅舎など、多くの人々の注目を集める建築のデザインに携わっている隈研吾が、人と人、人と物、人と環境をつなぐ思想と実践を語った新しい方法序説だ。自ら“ヴォリュームの解体”と呼ぶその方法論は、どのように培われてきたのか。また、金融資本主義的な“XLサイズ建築”の先に、どのような建築の未来を思い描いているのか。新型コロナウイルスによる外出自粛要請が発令される直前、隈研吾建築都市設計事務所にて行ったインタビューをお届けする。聞き手は、ライターの速水健朗。(編集部)
『負ける建築』から『点・線・面』へ
ーー今回の『点・線・面』は、現代建築へのシニカルな批判も含む建築批評であり、かつて『10宅論』(ちくま文庫/1990年)など若き辛口批評家だった隈研吾が戻ってきたという感触でした。それと同時に、隈さんが実践している建築理論を改めて解説する本でもあります。本書では、20世紀的なコンクリート建築を環境に勝つことを目的とした“ヴォリュームの建築”と位置づけ、隈さんが実践しているのは“ヴォリュームの解体”であると書いています。ヴォリューム建築はすでに過去のものだと捉えているのでしょうか。それとも、今なお付き合っていかなければいけないものでしょうか。
隈:今は地球規模で人口が増加している時代であり、ヴォリューム建築は多くの人の営みを支える技術でもあるので、付き合わざるを得ないと考えています。自分の建築でも、その技術的恩恵を受けているものはあるし、例えば国立競技場にもコンクリートや鉄でできた部分はあるわけです。それに対して罪の意識があるからこそ、自戒を込めてシニカルに書いた部分はあるかもしれない。もしヴォリューム建築から完全に脱却できていたら、こういう内容にはならなかった気がします。建築家という職業が持つ罪を意識していたからこそ、批判的に考えるようになったのでしょう。
ーーコンクリートへの自己批判的な姿勢は、周囲の環境と調和する建築を提唱した『負ける建築』(岩波書店/2004年)から脈々と続くものだと思います。このタイミングで新たに本書を執筆したきっかけを改めて教えてください。
隈:『負ける建築』を実際に執筆していたのは90年代前半頃でした。自分で言うのもなんですが、今読み返すと八つ当たり的な文章を淡々と書いていて、あまり論理的ではないと思います(笑)。80年代末に書いた『10宅論』も、安藤忠雄さんなど上の世代への八つ当たり的な部分があったけれど、まだ形式的に整理されていた。“負ける建築”という言葉を思いついたときは、上の世代と自分がやっていることの明確な違いがわかったとの実感がありましたが、それ以外の論理は支離滅裂。だから、その負け方、ヴォリュームの解体の仕方について、『負ける建築』の執筆から25年かけて勉強したことや実践を踏まえて、もう少しロジカルに文章化したいと思いました。例えば、物理的に大きな建築を作るときに、どのようにして負けるのか。その解答として、細かいパーツを組み合わせて作ることによってヴォリュームを粒子化するという手法がありますが、粒子が細かすぎると、遠くから見ると逆に大きな塊に見えてしまうとか、粒子が大きすぎると、一つひとつが目立ちすぎてオブジェクト的に見えてしまうということは、実践を通して理解していきました。
ーー本書の「線路の砂利という自由な点」の節では、線路の砂利は接着されることなく、それぞれ自由に動く点だからこそクッションになっていると気付き、その発想がその後の建築のヒントになったと書いています。他に『負ける建築』以降で学んだ具体的なことには、例えばどんなものがありますか。
隈:木の使い方はだいぶ変わったと思います。『負ける建築』を書いていた頃、梼原町地域交流施設(現・雲の上のホテル/1994年)の建築で木を使い始めていたけれど、扱いがすごく難しい素材で、今の感覚からするとまだ試行錯誤の段階だったと思います。木を構造的に成立させたり、隙間なく並べたりするのはとても難易度が高くて、コンクリート建築なら経験があまりなくてもある程度のものは作れるのですが、木ではそうはいかない。木で粒子的な建築を作ろうと考えたとき、隙間をどう埋めていくかは大きな課題でした。また、同じ木でも杉とか檜とか、使う木材によって性質がまったく違っていて、引いた線が想定していたものと違うものになってしまうことがありました。その辺の感覚は、幼稚園生が書道の練習をするように、一から経験を積み重ねてやっとわかったことです。
ーー今でこそ隈さんの建築といえば木のイメージがありますが、木の建築の権威というイメージではないんです。むしろ後から付いたイメージです。個人的には、ブロックの素材として水を使った「水ブロック」(2007年)に代表されるような新しい素材と組み合わせのアイデアにこそ隈研吾さんらしさを感じてきたのですが、ご自身ではどのように捉えていますか。
隈:木を使い始めて気づいたことは二つあって、一つは先ほど言ったように木は非常に奥深い素材だから幼稚園から始めなければいけないということ、もう一つは奥深い素材であるがゆえに、使い始めると即席で巨匠であるかのように偉そうに振る舞う人も多いということ(笑)。僕自身は、地道にきちんと経験を積んでいきたいと思っていたけれど、参考になりそうな先例はあまりなくて、だからこそあえて素人っぽい実験的な作品に挑戦することで、偉そうにならないように気をつけてきたつもりです。水ブロックなんて、今までの建築の流れにまったくなかったような、ある意味ではおもちゃみたいなものですが、そういう実験を自分に課すことによって巨匠的な振る舞いにならないようにしています。
ーー本書では、日本の伝統建築についての記述もありますが、単に昔からの技術が優れているということではなく、それをご自身でどう解釈して利用していくかを理論立てて丁寧に説明していますよね。
隈:日本の木造建築の歴史の中にも、大胆な実験や発想の転換がたくさんあります。予算という制約がある中で、いかに増築・改築をしていくかを考えたことで、何度もブレイクスルーを経験して、世界に例のないフレキシブルなゆるいシステムになっているのですが、そういうことはほとんど誰も教えてくれない。若い建築家などは、木造というだけで深遠なる技術体系があるかのように感じて敬遠してしまいがちですが、今後いかにヴォリュームを解体するかを考えたときに、そのような秘密主義的な権威主義はマイナスにしかならないのではないかと思います。
ーー隈さんは建築家として、日本の各地方や中国など様々な場所で建築を行ってきました。ゼネコンを含めて、業界全体にはどのような変化を感じていますか。
隈:個人的に感じた変化でいうと、年の功というか、長年やってきたことの蓄積でいろんな計画が通りやすくはなりました。水ブロックに関しても、40歳の人間が提案していたら「冗談でしょう」と言われていたと思いますが、60歳の人間が提案すると「試しにやってみましょうか」となる。建築業界にはそういうヒエラルキーを重視するような縦社会があると思います。経験を積んだことで、むしろ実験的なことはやりやすくなったかもしれません。
ーー水ブロック以外でも、ETFE素材による移動可能なモバイルハウス「800年後の方丈庵」(2012年)を建築するなど、隈さんは今も実験的な仕事を色々としています。一方で、レム・コールハース『S,M,L,XL』でいうところの非常に大規模な「XLサイズ建築」にも携わっていますが、建築の規模感による意識の違いはありますか。
隈:向き合い方は大きくは変わりませんが、Sサイズ建築に近いほど実験的なことはやりやすいです。Sサイズ建築で実験したことを、XLサイズ建築でどのように拡張するかを考えるケースが多いですね。Sサイズ建築とXLサイズ建築を往復することが自分にとって必要で、それは村上春樹が短編小説と長編小説の両方が自分にとって必要だと言っているのと近いかもしれません。いろいろな短編を書く中で、これは長編になりうるというものを見つけて、長編に取り掛かるのですが、長編ばかりを書いているとフラストレーションも溜まるから、また短編に戻るという。
建築における、新しい時間の捉え方
ーー先日、隈さんが駅舎のデザインを手がけた高輪ゲートウェイ駅が開業しました。点字ブロックが従来の黄色ではなく、ライトイエローになっているところなどが新鮮で、大規模建築でも新しいことに挑戦していることが伺えました。
隈:あの点字ブロックは、東京大学分子細胞生物学研究所で視覚障害者の研究をしてきた伊藤啓准教授の提案から開発したもので、実は濃いイエローより視認性が良いんです。面白いアイデアが出たときに、実現に向けてうまく一緒に走れるパートナーがいるのは、僕にとって一番大事なことの一つです。
ーー建築は、常に新しいテクノロジーとともに発展してきた側面もあると思います。隈さんの提唱する「負ける建築」は、現代的なテクノロジーを否定して環境と調和しようとするのではなく、むしろ積極的に活用しようとしていますよね。
隈:新しいテクノロジーへの関心はすごく強いです。1980年代半ばから米国コロンビア大学でコンピューテーショナル・デザインやパラメトリック・デザインの研究が行われるようになり、僕はちょうどその頃に研究員としてコロンビア大学に行っていたから、その影響があるのでしょう。しかし当時、「これはすごいことが始まった」と感じてはいましたが、一方でコンピュータが描くグニャグニャのデザインには違和感もありました。その違和感の正体を、約5年前に理論的に説明してくれたのが建築史家のマリオ・カルポです。建築史の聖書というくらい有名なレイナー・バンハムの 『第一機械時代の理論とデザイン』(1976年)という本では、機械には機関車や船などのデザインの「第一マシンエイジ」と、テレビやラジオなどのデザインの「第二マシンエイジ」があって、それらはまったく異なるものだと説明しています。同じように、コンピューテーショナルデザインにも第一マシンエイジと第二マシンエイジがあり、僕が無意識に志向した粒子の集合という考え方は、コンピューテーショナル・デザインでいうと第二マシンエイジなんだと、カルポは指摘してくれました。
ーー『点・線・面』というタイトルは、画家・カンディンスキーの『点・線・面―抽象芸術の基礎』(1959年)のオマージュですが、本書の理論が整理されたのは、マリオ・カルポの指摘によるところが大きいのでしょうか。
隈:カルポの指摘で、自分の方法論を再確認できたところはあると思います。カンディンスキーについては、初めて読んだのは高校生の頃で、実は当時はつまらない本だと思っていました(笑)。無理に話を小難しくしている印象があって、ずっと本棚に置いたままでした。でも、この本を書くにあたって読み返してみたところ、面白く感じる部分がたくさんあった。中国の尖っている屋根は点であるとか、版画において木版と石版と金属版では時間の概念が違うとか。カルポの指摘の後に、カンディンスキーの本を読んで、書くことが固まっていった感じです。
ーー時間の話でいうと、本書では絵画におけるキュビズムの空間と時間についての理論に触れる箇所もあります。建築史家のギーディオンが、キュビズムの理論を建築に応用したことについては批判的に書かれていますが、自動車や飛行機が登場したことで、それまで体験したことのない速度での移動が誕生し「運動=時間」論が流行し、デザインなどにも表れていく。現在のコロナウイルス騒動は人々のグローバルな移動によってもたらされたものですよね。そう考えると移動について見直す動きが出てくるかもしれない。
隈:ギーディオンの『空間・時間・建築』は未だにモダニズム建築の聖書と言われていて、その理論の中心となっているのが、今言ったような「運動=時間」論なんですけれど、改めて読み返すと、これが驚くほどつまらなかった。「運動=時間」という概念自体がもはや退屈なものになっていると思います。移動し続けることが常態化していて、それゆえにすべてが止まっているのと同じようにも感じられる現代には、新しい時間の捉え方が必要なのかもしれません。移動なんて少しも驚くことではないし、そのままでは表現たりえない。現在の量子力学では、これまでのように移動を軸にして時間を捉えるのではなく、まったく別の形で時間を捉えなおそうとしています。だから僕は、物質がそこにあること自体がすでに時間であると考えます。例えば、物質が風化していくという時間もあれば、入れ子構造で変化していくような時間もある。観光地の建築でいえば、その場所に積み重なっていった時間が、その建築の中に入れ子状に立ち現れるようなものを作れないかと思っています。その場に積み重なった時間を体験するために、人々が訪れるような建築です。
ーー現在、人々がなかなか移動できない状況が続いています。どう感じていますか。
隈:1月からぜんぜん移動ができていなくて、体のリズムが変わってきたと感じています。時速何キロで移動するのが必要とか、そういう20世紀的な時間感覚ではなく、移動することそのものが自分の肉体にとって刺激のあることで、一種の健康術みたいなものだったのかなと。僕の場合、物を書くのはほぼ100%、飛行機とかで移動しているときで、その方がなぜか書きやすい。移動するスピードは関係なくて、移動している最中というのがポイントかもしれません。
ーー新幹線や飛行機だと、書き仕事が捗るという話はよくありますね。隈さんにとって、建築の仕事と書く仕事はどう関連しているのですか。
隈:それはすごくはっきりしています。建築の仕事のほとんどは、現場の工事のチームとの細々した打ち合わせか、クライアントのチームとビジネス的な打ち合わせで、極めて現実的な形而下的側面ばかりです。そして、そういう現場にずっと浸かっていると、自分が何をやっているのかが見えなくなってくる。そういうときに、自分の仕事を一つのシナリオに落とし込むようにして文章化すると、考えが整理されて、今やっていることの意味が見えてきて救われるのです。逆にいうと、僕の場合は書いていないとやっていられない。現場はそれぞれの極めて現実的な世界のリズムで動いていて、僕にとってはその間の飛行機での移動中だけが自由になれる時間だから、そこで書くのがタイミング的にベストなんだと思います。
金融資本主義とXLサイズ建築
ーールネサンス的なMサイズ建築から、産業革命的なLサイズ建築へ、そして20世紀後半の金融資本主義的なXLサイズ建築へという流れについて、もう少し詳しく教えてください。現在も金融資本主義の時代は続いていると思うのですが、その中で隈さんはレム・コールハースらXLサイズ建築を得意とする建築家をどう捉えていますか。
隈:コールハースは2月にニューヨークのグッゲンハイム美術館で『カントリーサイド、ザ・フューチャー』という展覧会をやっていたのですが、材料やディティール、切り口などは僕が目指すものと近いと感じました。彼とは時々会っていて、先日も日本酒を飲みながら話す機会があったけれど、禅の境地に達しているような感じで、これまでとは違う方向に歩んでいるのかなと。彼が北京に設計したCCTVの本社ビル(2008年完成)が、習近平などに「奇々怪々建築」と批判されたあたりから、金融資本主義的な現実と距離を取り始めていると思います。ちなみに彼はものすごい日本マニアで、日本酒にも詳しいし、建築家としても篠原一男の70年代の建築に興味があるみたいです。
ーーこの本ではコールハースの流れでザハ・ハディドにも触れています。もう少し多く触れてほしかったなという思いがありました。隈さんは、彼女とは、どの程度の接点がありましたか。
隈:ザハとは、コンペの最終審査で5~6社に絞られたところで、何度も一緒になっています。彼女は話すプレゼンテーションがすごく上手いタイプではないけれど、そのデザインは模型やレンダリングで映えるから、コンペにすごく強くて、僕は負けることが多かった。だからこそ、僕にとってはコールハースとともに研究対象でしたし、シニカルに見ていた部分もあります。彼女の建築デザインは、金融資本主義における商品の形態としてすごくインパクトがあったと思います。だから彼女が亡くなってからも、彼女の事務所は大きなXLプロジェクトをとり続けています。
ーーザハに負け続けてきた隈さんが、結果国立競技場にかかわるというのは皮肉な結末ですね。ザハのデザインの国立競技場が実現しなかったことの主な理由が、国内の大御所建築家を含む、国内からの横槍だったこと。そして、その理由として莫大な建設費があげられました。
隈:ザハの造形能力は、まさに金融資本主義時代のディーバと言えるものだと思います。コールハースには自分でやっていながら自己批判的なシニカルな視点があるけれど、ザハはXLサイズ建築の可能性を極点まで突き詰めた人だと思いますし、それはそれですごい能力だと思います。
ーー本書ではコールハースとともに、磯崎新の都市論、建築論なども批判の対象になっています。彼らの世代は、小さな建築が次第に大きくなり、ついにはアジアの混沌の中でXLサイズまでに爆発的に膨張したことで、世界は終末的な状況に陥ったという悲観論をしばしば語り、自分だけが状況を的確に把握した賢者であるかのように振る舞い、巷の建築家を見下していると。
隈:その部分は、磯崎さんが僕の国立競技場のデザインを辛辣に批判してくれたからこそ、書けたものです。ちゃんと反論すべきだと思って書きました。建築業界における磯崎さんの言説の影響は非常に大きくて、80年代以降の日本の建築家は誰もが磯崎さんの知的な書きぶりに圧倒されてきたと言ってもいいくらいです。僕もずっと敬意を抱いてきました。建築業界にはヒエラルキーがあると言いましたが、その意味でも、自分の考えをこういう形で発表できたのは良かったです。そもそも僕らの世代はXL状況の中で建築家としてスタートして、コールハースがXLの元凶とするアジアに生まれ育っているので、その現実を受け入れた上で、アジアの可能性と未来を考えたいんです。
■書籍情報
『点・線・面』
著者:隈 研吾
発売日:2月7日
定価:本体2,200円+税
出版社:岩波書店
'■etc > 책 book' 카테고리의 다른 글
| 2015년 마루젠에서 (0) | 2016.10.03 |
|---|---|
| 카밀로 지테. Camillo Sitte (0) | 2016.03.15 |
| Collective Housing in Holland (Process Architecture Series) (0) | 2016.03.14 |
| 예전 블로그글 - The Modern Urban Landscape (Edward Relph) (0) | 2016.03.14 |
| 도쿄의택지 형성사 都市住宅形成史 Tokyo Estate / 하세가와 토쿠노스케 長谷川 徳之輔, 1988 (0) | 2016.02.27 |